岩尾醤油醸造元について|人気のうめ醤油|福井の老舗「岩尾醤油醸造元」
岩尾醤油醸造元について
about
- トップページ >
- 岩尾醤油醸造元について
醤油と味噌の歴史
醤油の歴史

醤油は、遠く奈良時代の醤(ひしお)という発酵食品や鎌倉時代の溜(たまり)と呼ばれる調味料にその原形がみられますが、大豆と小麦を原料にした今日の醤油に近いものは、戦国時代に生まれました。
文献に醤油の文字が登場するのは室町時代ですが、それより数百年前の平安時代には醤油のルーツといわれる「醤(ひしお)」が作られていたようです。ひしおは、当時の塩蔵発酵食品の総称で、草びしお、肉びしお、穀びしおの3種類に分かれていました。草びしおは今の漬け物、肉びしおは塩辛類、穀びしおが醤油のようなものだといわれています。
企業の形で生産されはじめたのは、もう少しあとのことですが、それでも醤油産業はざっと400年の歴史と伝統をつづっています。
(日本醤油協会 文献より)
醤油ができるまで
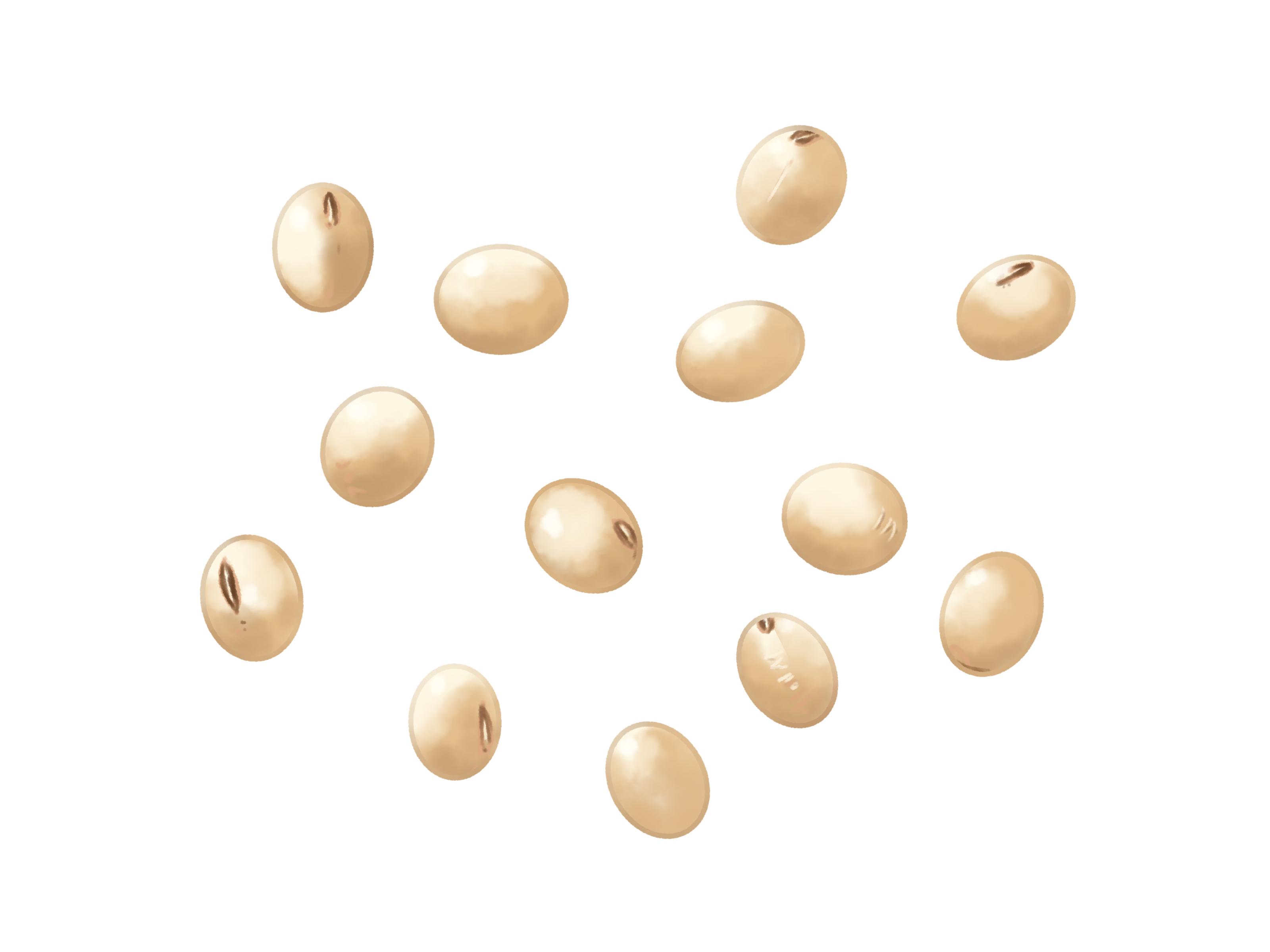
1.大豆に水を加えて蒸します。

2.同時に小麦は炒って引き割ります。
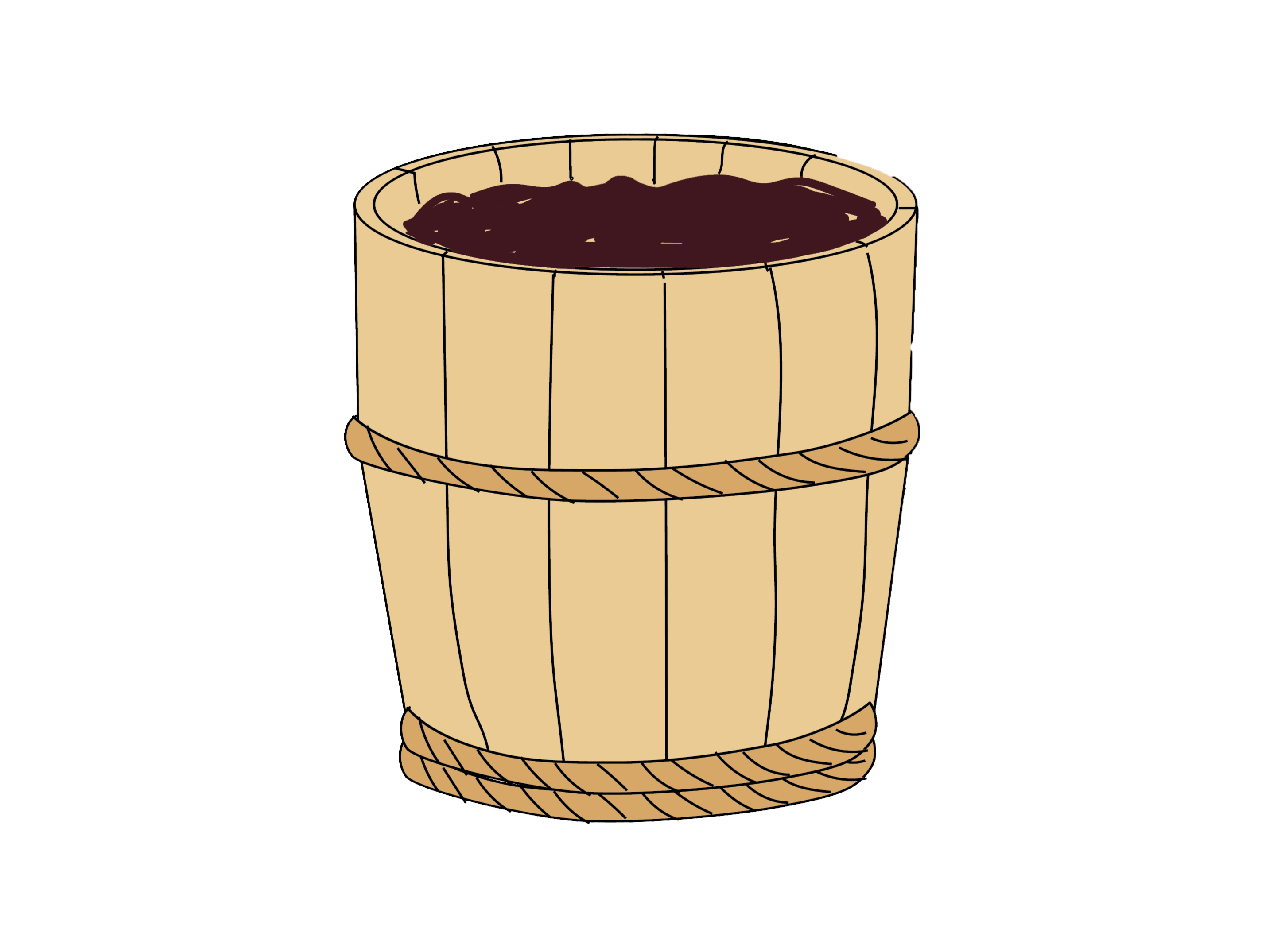
3.蒸した大豆と引き割った小麦を混ぜ、そこに種麹を加え、麹室に移動します。

4.混ぜた麹に塩を溶かした塩水を加え、発酵・熟成させて、もろみを作ります。
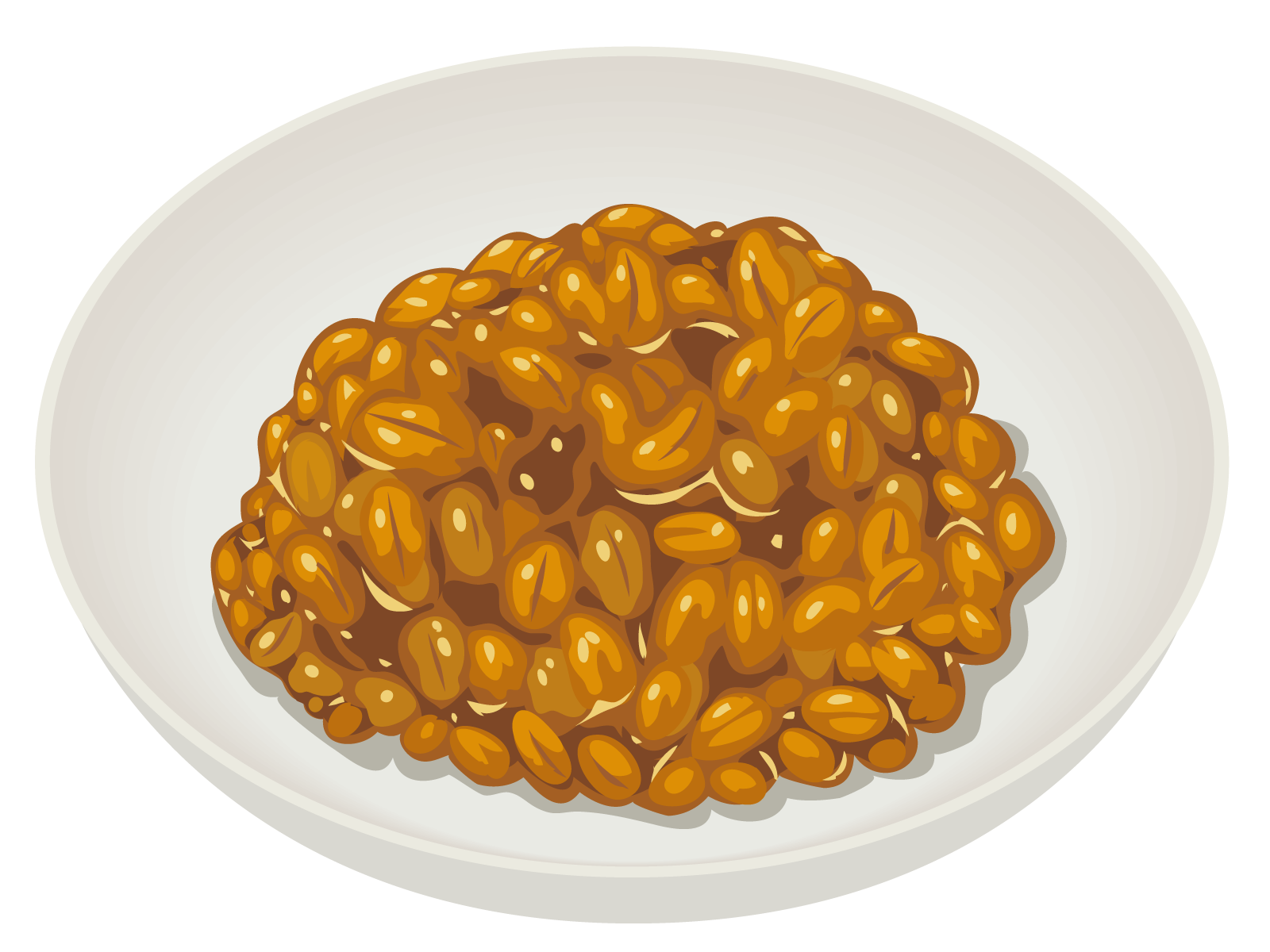
5.できたもろみをしぼり、加熱して色・香り・味を調えます。

6.検査室で検査を行い、問題が無ければ容器に詰められ店頭に並びます。
味噌の歴史

日本の文献に「味噌」が最初に登場するのは奈良時代。中国大陸から伝わったもので、「醤(ひしお)」、「未醤(みしょう)」と呼ばれていました。そのころは寺院や貴族だけが口にできる贅沢な食べ物で、製法も食べ方も現在と比べ多少異なります。その後日本の風土にあった発展を遂げ、戦国時代を迎えるころには現在の「味噌」となっていたようです。当時の武将はその優れた栄養価と保存法に着目し、武士に携行させたといわれ、これを機会に広く庶民の間に普及していったのです。
(味噌健康づくり委員会 文献より)
味噌ができるまで
大豆を洗う
味噌作りの第一歩は、大豆を丁寧に洗うことから始まります。大豆の表面についた汚れや不純物をしっかり取り除くことで、発酵の妨げを防ぎ、味噌本来の風味を引き出します。大量の水を使い、数回に分けて優しく洗い流し、清潔な状態に整えます。この工程を丁寧に行うことで、大豆が水を均等に吸収し、後の蒸しや発酵の過程がスムーズに進みます。

水に浸す
洗浄後の大豆はたっぷりの水に浸し、じっくりと吸水させます。浸水時間は季節によって異なり、夏は約10時間、冬は約20時間が一般的な目安です。この工程により、大豆が均等に膨らみ、蒸しや煮の際にムラなく火が通るようになります。また、発酵を促すための準備段階でもあり、しっかりと水を含ませることで、味噌の仕上がりが滑らかで深みのある味わいになります。

蒸す・煮る
水に浸して膨らんだ大豆は、蒸すまたは煮ることで柔らかくします。蒸す場合は、旨みを逃さず濃厚な味噌に仕上がります。一方、煮る場合は、大豆がより柔らかくなり、滑らかな味噌ができます。どちらの方法でも、大豆が指で軽く潰せるほどの柔らかさになるまで火を通すことが重要です。この工程を丁寧に行うことで、発酵がスムーズに進み、味わい深い味噌が完成します。

つぶす
柔らかく蒸した、または煮た大豆は、味噌の食感を決める大切な工程として丁寧につぶします。すりつぶし方によって、なめらかな味噌や粒感を残した田舎味噌など、仕上がりの個性が変わります。手作業や機械を使い、大豆が均一になるようにつぶすことで、麹や塩と混ざりやすくなり、発酵が均等に進みます。この工程が、味噌の風味と食感を大きく左右します。

大豆・米麹・塩・水を混ぜ、仕込む
つぶした大豆に米麹と塩を均一に混ぜ、水を加えて仕込みます。しっかり混ぜることで、麹の力が全体に行き渡り、発酵がスムーズに進みます。この工程では、空気が入りすぎないように注意しながら、味噌玉を作り、容器に詰めて表面を平らにならします。最後に塩をふり、カビの発生を防ぎます。仕込みを丁寧に行うことで、熟成が進み、旨みと深みのある味噌に仕上がります。

発酵・熟成させる
仕込んだ味噌は、時間をかけて発酵・熟成させることで、豊かな風味と深みが生まれます。発酵の過程で、麹菌や酵母が働き、大豆の旨みを引き出しながら味噌独特の香りとコクを生み出します。熟成期間は数か月から1年以上で、温度や湿度によって味の変化も異なります。じっくり寝かせることで、まろやかで奥行きのある味噌へと仕上がります。

製品の完成
じっくりと発酵・熟成を経た味噌は、豊かな風味と深いコクを持つ製品として完成します。熟成が進むことで、色や香りが変化し、味わいに奥行きが生まれます。完成した味噌は、容器に詰められ、家庭や飲食店へ届けられます。自然の力で育まれた味噌は、料理に旨みを加え、毎日の食卓を彩る、日本の伝統的な発酵食品です。

旅館
白浜荘
〒910-3372
福井県福井市西二ツ屋町2-1
TEL:0776-86-1316(代)
FAX:0776-87-2828
■車でお越しの方
北陸自動車道福井北ICより車で国道416号線を西へ30分、国道305号線左折2分。
駐車場無料、50台分。
■電車でお越しの方
JR「福井駅」近くの京福バス「鮎川」行きバスに乗車。「浜中」停留所で下車し、徒歩1分です。
CMでおなじみの、かにの早むき名人「むきむきみっちゃん」名物女将のお宿です。すべてのお部屋に必見の技を披露しに上がります。

小玉旅館
〒910-3552
福井県福井市茱崎町13-113
TEL:0776-89-2006
FAX:0776-89-2375
■北陸自動車道ご利用の場合
敦賀IC~国道8号線~国道305号線で約1時間
金津IC~国道305号線で約1時間
■JR線、えちぜん鉄道勝山永平寺線、えちぜん鉄道三国芦原線福井駅から京福バスご利用の場合
京福バス“78番線越前海岸左右行き”
福井駅前~茱崎第2で約1時間
茱崎第2より徒歩3分

料理旅館 石森亭
〒910-3377
福井県福井市浜住町8-3
TEL:0776-86-1518
FAX:0776-86-1519
■北陸自動車道ご利用の場合
敦賀IC~国道8号線~国道305号線で約1時間 金津IC~国道305号線で約1時間
■JR線、えちぜん鉄道、福井駅から京福バスご利用の場合
京福バス 越前海岸ブルーライン 系統番号(10,11,17)波の華行き 浜住下車
えちぜん鉄道三国芦原線、三国駅 京福バス海岸線 系統番号(98)和布行き 浜住下車

樽海
〒910-3554
福井県福井市浜北山町1-2
TEL:0776-89-2311
FAX:0776-89-2066
北陸自動車道の敦賀ICより、国道8号線、国道305号線を経由の場合(合計 約80分)
北陸自動車道の鯖江ICより、国道417号線、国道305号線を経由の場合(合計 約60分)

お店
出雲記念館
〒918-8026
福井県福井市渕2-2001
TEL:0120-1150-16
■お車でお越しの場合
福井ICから車で約25分
駐車場スペース 120台

八雲迎賓館
〒918-8026
福井県福井市渕4-708
TEL:0120-642-896(10:00~19:00)
定休日 火・水曜日

居酒屋 花や
〒910-0023
福井県福井市順化2-19-15
TEL:0776-26-0980

リカーショップ まつやま
〒910-0005
福井県福井市大手3-12-10
TEL:0776-22-4423
FAX:0776-22-4427
アクセス:JR線、えちぜん鉄道勝山永平寺線、えちぜん鉄道三国芦原線 福井駅西口より徒歩7分
営業時間 10:00~20:00
定休日 日曜日・祝日




